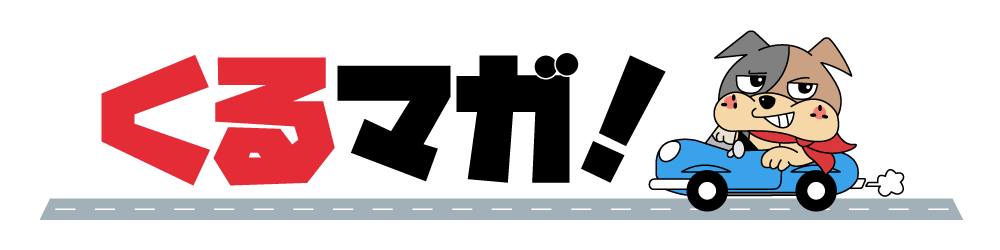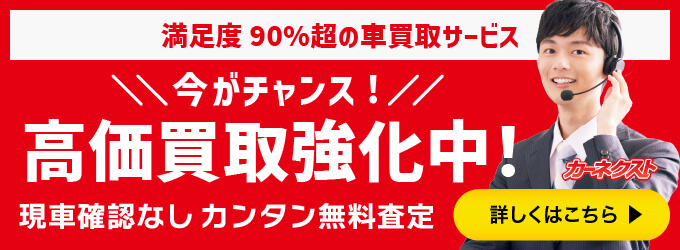久しぶりにF1のレースをテレビで見たら、昔とエンジン音が違ってビックリした…ルールがよくわからない…もっと白熱のカーチェイスが行われるイメージだった…など様々な声をよく聞きます。
それもそのはず、毎年変更されてきたレギュレーション内容により、この70年でエンジンやタイヤの幅、フレームの詳細に至るまで試行錯誤が繰り返されてきました。
F1レギュレーション変更の詳細

どんな競技でもルールは付きものですが、F1のように毎年変わる競技も珍しいものです。
例えばスキージャンプやアイススケートのルール改定で、日本人選手が苦戦を強いられている姿をオリンピックで見かけることはありますよね。それでも改定されてからそこに照準を合わせて練習を積んでいけば、最終的にはどの選手にも平等に勝利への道が開かれているとも考えられます。
F1の場合は常にどのチームもレース用の車の開発と先を見越した開発が行われており、昔のように伝説的なレーサーの有無よりも、資金面・情報面での勝敗がものを言うのが現状のようです。
| 変更時期 | レギュレーション変更内容 |
|---|---|
| 1948年~1953年 | 排気量のみ制限あり:過給機付きなら1500ccまで / 過給機無しなら4500ccまで 過給機とは、普通に酸素を燃やすよりも多くの空気を取り込んで効率よく燃焼エネルギーを得られるようにする装置のこと。 特に高度で空気の薄くなった場所でも空気を取り込めるように、軍用の航空機において開発されていたもの。 この時点では、車両そのものの馬力には制限を施しているが、その他の重量や形などには詳細は決められず。 戦後の疲弊した市民の余暇として誕生したモータースポーツの存在意義が窺われる。 |
| 1954年~1960年 | 排気量が、過給機付きなら750ccまで / 過給機無しなら2500ccまで この時から使用するガソリンの種類が指定される。 排気量は当初よりも小さくなり、それに比例して車の軽量化が進む。 |
| 1961年~1965年 | 過給機の搭載が無くなり、排気量は自然吸気のみ1300cc~1500ccまで 車体の重量を車検にて測るようになり、冷却水およびエンジンオイルなども併せて 450kg以上は無ければならないとされる。 |
| 1966年~1969年 | 最低重量が450kgから500kgにアップ リアウィングの接触事故が増えたことを受 けて、その高さ・幅の規定、可動禁止などの項目が加えられた。 火災事故の多発により車に消火器を搭載することが義務付けられた。 |
| 1970年~1977年 | 最低重量が500kg→530kg→550kg→575kgにアップ 燃料タンクに断熱性の高い積層ゴム素材を使用することを義務付けられ、保護の役割を果たすモノコック側面衝撃吸収構造を採用。 モノコックとは、それまで鋼管を繋いで空洞のフレーム=スペースフレームで車体を造っていたものを刷新し、 薄いアルミ板を箱型に形成して車体を造る形式のこと。 燃料タンクがむき出しにならず、事故率が低下するメリットに繋がる。 |
| 1978年~1983年 | 車体全長5000mm、最大車高850mm(→950mm)、最大車幅2150mm、最大タイヤ幅530mmに制限 最低重量580kgにアップするも、新素材カーボンファイバーの台頭により540kgまで軽量化。 サバイバル・セル・コクピットでなければならない=モノコックの構造を義務化。 |
| 1984年 | 燃料タンク220Lまでに制限 給油が原因の火災が相次ぎ、レース途中の給油を禁止される。 |
| 1985年 | リアウィングにおける補助のウイングレットを禁止 年に決められた回数のクラッシュテストを義務化。 後にウイングレットについては、リアウイングではない部分に空気圧を計算して 取り付けられるのが主流になる。 |
| 1986年 | あらためて、排気量が最大1500ccまでに制限 / 燃料タンク195L ターボエンジン車に限定される。 |
| 1987年 | 排気量が過給機付き1500ccまで(最低重量540kg) 過給機無しなら3500cc(最低重量500kg)まで、燃料タンクは150Lに制限される。 ここで過給機の有無ではなく、過給機の最大圧力に制限が加わる。ブースト圧を上げれば上げるほど異常燃焼による火災が発生しやすくなるための措置。 |
| 1988年 | 過給機の最大圧力に制限 過給機無しの車両に関しては燃料の使用量に制限なし。 ドライバーの足の位置を確保し、フロントアクスル=前輪の車軸の位置を統一。 |
| 1989年~1993年 | 過給機禁止 / 最低重量500kg以上 燃料の使用量は制限しないがレース中の給油は禁止される。 |
| 1994年 | 最低重量505kgとするも、ドライバーの過度な減量が非人道的であるとし、 途中から520kgに緩和される。 燃料タンクの開発が進み、レース途中の給油があらためて許可される。 |
| 1995年 | 過給機搭載禁止 最大排気量3000ccまで、最低重量595kgからになる。 レーサーの技術を上回るほどのアクティブサスペンション機能が資金のあるチームのみに 搭載されやすいことでレースの公平性を欠いているとし、禁止される。 |
| 1996年 | 最低重量600kg コクピット左右にレーサーの安全性を確保するためのプロテクターを搭載。 |
| 1997年~1999年 | リアウイングレットの高さ規制 車幅2000mm以下に制限される。 ガソリンをEUの市販燃料に統一する。 |
| 2000年以降~ | エンジンの形式を統一 クラッシュテストの速度引き上げる。 車体の詳細はミラーウイング、テールランプのサイズは拡大、地上と車の最低地点を100mm以上に引き上げ、コクピットの壁の厚みを確保する。 その他にはレースの運営に関する細やかなレギュレーションが毎年変更されていくことになる。 かけられるコストを一定ラインに抑えることを目的とした改正が多数見られる結果となる。 |
| 2019年 | コックピット保護のために「Halo」が追加された2018年の影響がどのように反映されるのか、新たなレギュレーションの行方が気になるところです。 |
まとめ

F1人気が昔よりも低下したと言われている背景には、レギュレーション変更の歴史が切っても切り離せない関係にあることがよくわかりました。操縦する運転手の命を最優先にすること以外に、どのチームにも勝利に平等であろうとし過ぎるがゆえに見ていて難解になるレギュレーション内容が、素人にF1への敷居を高くさせているのではないかと言われています。しかし見方を変えれば、「今年はどのようにレギュレーションが変更されるだろうか?」と楽しみながら優勝チームを予測する楽しみ方も、これから大幅に刷新されるであろうF1の見どころの一つではないでしょうか。